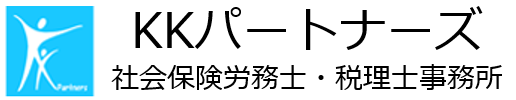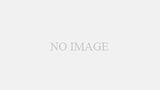1.改正の概要
令和3年4月21日,「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律第25号)が成立しました(同月28日公布)。
両法律は,所有者不明土地の増加等の社会経済情勢の変化に鑑み,所有者不明土地の「発生の予防」と「利用の円滑化」の両面から,総合的に民事基本法制の見直しを行うものです。
まず,「発生の予防」の観点から,不動産登記法を改正し,これまで任意とされていた相続登記や住所等変更登記の申請を義務化しつつ,それらの手続の簡素化・合理化策をパッケージで盛り込むこととしています。
また,同じく「発生の予防」の観点から,新法を制定し,相続等によって土地の所有権を取得した者が,法務大臣の承認を受けてその土地の所有権を国庫に帰属させる制度を創設することとしています。
次に,「利用の円滑化」を図る観点から,民法等を改正し,所有者不明土地の管理に特化した所有者不明土地管理制度を創設するなどの措置を講じることとしています。
なお,施行期日は,原則として公布後2年以内の政令で定める日(相続登記の申請の義務化関係の改正については公布後3年,住所等変更登記の申請の義務化関係の改正については公布後5年以内の政令で定める日)とされています。
両法律は,所有者不明土地の増加等の社会経済情勢の変化に鑑み,所有者不明土地の「発生の予防」と「利用の円滑化」の両面から,総合的に民事基本法制の見直しを行うものです。
まず,「発生の予防」の観点から,不動産登記法を改正し,これまで任意とされていた相続登記や住所等変更登記の申請を義務化しつつ,それらの手続の簡素化・合理化策をパッケージで盛り込むこととしています。
また,同じく「発生の予防」の観点から,新法を制定し,相続等によって土地の所有権を取得した者が,法務大臣の承認を受けてその土地の所有権を国庫に帰属させる制度を創設することとしています。
次に,「利用の円滑化」を図る観点から,民法等を改正し,所有者不明土地の管理に特化した所有者不明土地管理制度を創設するなどの措置を講じることとしています。
なお,施行期日は,原則として公布後2年以内の政令で定める日(相続登記の申請の義務化関係の改正については公布後3年,住所等変更登記の申請の義務化関係の改正については公布後5年以内の政令で定める日)とされています。
「民法等の一部を改正する法律」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」の概要
両法律の概要については,以下の資料を御覧ください。
なお,随時,参考資料を追加する予定です。
なお,随時,参考資料を追加する予定です。
- 概要[PDF:490KB]
民法等の一部を改正する法律
法律等については,以下の資料を御覧ください。
なお,随時,参考資料を追加する予定です。
なお,随時,参考資料を追加する予定です。
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律
法律については,以下の資料を御覧ください。
なお,随時,参考資料を追加する予定です。
なお,随時,参考資料を追加する予定です。
- 法律[PDF:125KB]
2.改正の影響
所有者不明土地問題を背景に、「遺産分割は、相続開始後10年経過したら、特別受益や寄与分を考慮しない」という改正も予定されています。
なぜ、そうした改正が行われるかといえば、遺産分割が行われないと登記名義人が何代も前のままとなり、その権利者を特定するのに時間とコストがかかる為です。
具体的な影響としては、生前贈与を受けた相続人とそうでない相続人間で、相続開始後10年以内に分割が完了しないと生前贈与を受けていない相続人は特別受益が考慮されないため不利益を被る可能性があります。
但し、事前に家庭裁判所へ遺産の分割を請求しておけば、自動的に取り分が減ることはなくなるため、今後は遺産分割に関する家庭裁判所での調停が増加するものと考えられます。